
離職時の事務手続きとして、健康保険証、社会保険、年金、税金などの重要な手続きがあります。
このような事務手続きは離職後2週間以内に再就職していれば、新しい会社の総務部から書類をもらって提出すれば会社が済ませてくれますが、そうでない場合は自分で手続きをしておかなければなりません。
本記事では、公的な事務手続きのポイントをお伝えします。
転職先が決まっている場合と転職先が決まってない場合

転職先が決まっている場合は、総務に【源泉徴収票】【年金手帳】【雇用保険被保険者証】【健康保険被扶養者異動届】を提出します。
転職先が決まってない場合は、【地方税(普通徴収)納付】【国民年金加入】【健康保険を選択して加入】【以前の会社で離職票をもらい、失業手当の受給資格確認と受給手続き】を自分で行います。
離職時の事務手続き、それぞれのポイント

地方税
地方税は住民登録している自治体の住民税などですが各自治体により税額が違います。
通常は前年度分を6月から翌年の5月分の給与から天引き徴収される後払いです。退職時には残額を最後の給料から全額納入しなければいけませんが、6月から12月の間に辞めた場合は金額が大きいため、分納(4分割)も可能です。
(分納の場合は納付書が送られてくるので、それと共に自分で支払います。失業中でも支払い義務はあります。)
転職先で手続きを行ってくれるのは今年度分からなので、前年度分については各自治体の地方税の部署に電話で問い合わせるなどして確認しましょう。
所得税
給与所得に対してかかる税金で給与から天引きされています。
概算で天引きされているので年末に調整されて余分に払った分は返金されます。(年末調整)
退職時には会社から【源泉徴収票】をもらって保管しておきます。
【年末調整】や【確定申告】をする時に必要なので大切にしましょう。
次の仕事に就かないまま年を越した場合は、【確定申告】を自分ですると、納めすぎた分が戻ってきます。
「確定申告などややこしいなあ」と思わず、税務署で相談すれば無料ですし、案外親切に教えてくれますよ。
公的年金
民間企業が加入している公的年金は【厚生年金保険】ですが、保険料の半分は会社の負担で後の半分は給与から天引きされています。
退職して次の勤務先に社会保険が完備されていない場合は国民年金に加入する必要があります。
転職先が決まらず失業中も自分で国民年金に移行する必要があります。
失業中は保険料が免除される制度もありますから、これを活用してもいいです。
転職先に社会保険がある場合は年金手帳を提出すれば会社が手続きしてくれます。
離職期間が長引いても2週間以内に自分で、市区町村の年金課に行って年金の種別変更をしてください。
健康保険
社会保険完備の会社では、年金と同様に健康保険も半額負担してくれていますが、退職によって以前の会社の被保険者資格がなくなるので、健康保険証を会社に返却しなければなりません。
退職後2週間以内には自分で、市区町村の健康保険課で国民健康保険の加入手続きをしてください。
健康保険のブランクができないように注意が必要です。
転職先が決まっている場合は、その会社の被保険者になるので会社が手続きをしてくれます。
雇用保険
雇用保険はアルバイトや契約社員でも条件を満たせば加入してくれます。
これも、保険料は勤務先と本人の折半です。
退職時には【雇用保険被保険者証】を受け取ります。
転職先が未定の場合は【離職票】をもらいましょう。
【離職票】と【雇用保険被保険者証】を持ってハローワークに行けば条件にのっとり【失業手当】や【再就職手当】などが支給されます。
煩わしい事務手続きですが、生活の基盤をしっかり整えておくことが一番大事ですから、この際少し覚えておくと安心です。
それに、最近の公的機関はかなり親切で何でも教えてくれますから、わからないことは電話して確認してから行うことをおすすめします。





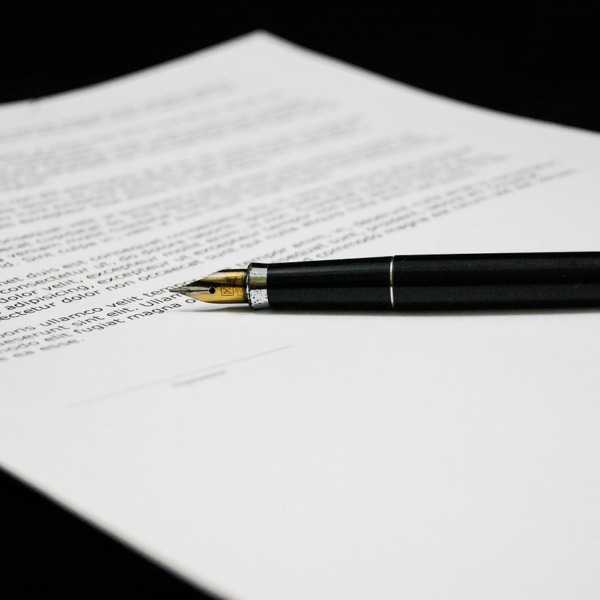



コメント